『保育士の離職を減らすために』のテーマで講師として登壇(谷本慎二)

代表の谷本が、社会福祉連携推進法人あたらしい保育イニシアチブ主催の『Z世代が分かる!離職対策』セミナーに講師として参加しました。
保育事業者に向けて『保育士の離職を減らすために』をテーマに累計3万件以上の退職代行のデータを元に講演を行いました。
講演会やコンサルティングなどのご依頼は、MOMURI+(モームリプラス)問い合わせフォームまたはLINEで承っております。
講演実施の背景
この度、社会福祉連携推進法人あたらしい保育イニシアチブより「離職対策が課題となっている保育業界に向けて講演をしてほしい」とのご依頼を受けました。
社会福祉連携推進法人あたらしい保育イニシアチブは「次世代に必要とされる保育園をつくる」を理念に、全国約40法人300施設が集う日本初の保育に特化した社会福祉連携推進法人です。
過去には11回の講演を行い、今回で12回目の登壇となります。
過去のセミナー講演実績
- 看護師の離職対策カンファレンス(主催:アウトカムマネジメント株式会社)
- 退職防止講演(主催:東京都信用金庫協会)
- 人材流出防止セミナー(主催:彦根商工会議所)
- 新卒の離職率低下について(主催:大学職業指導研究会)
- 看護師等の離職防止・定着促進セミナー(主催:総合メディカル株式会社)
- 総院長ゆうきゆう先生と弊社代表の対談(主催:ゆうメンタルクリニック)
- コールセンター従事者(企業)向けセミナー(主催:株式会社リックテレコム)
- ブラック企業の見極め方(主催:私立大学)
- 医療従事者の人材定着率向上について(主催:総合メディカル株式会社)
- 製造業従事者の離職防止策(主催:株式会社パソナ)
- やめない会社をつくるために(主催:株式会社新潟日報社)
講演の概要
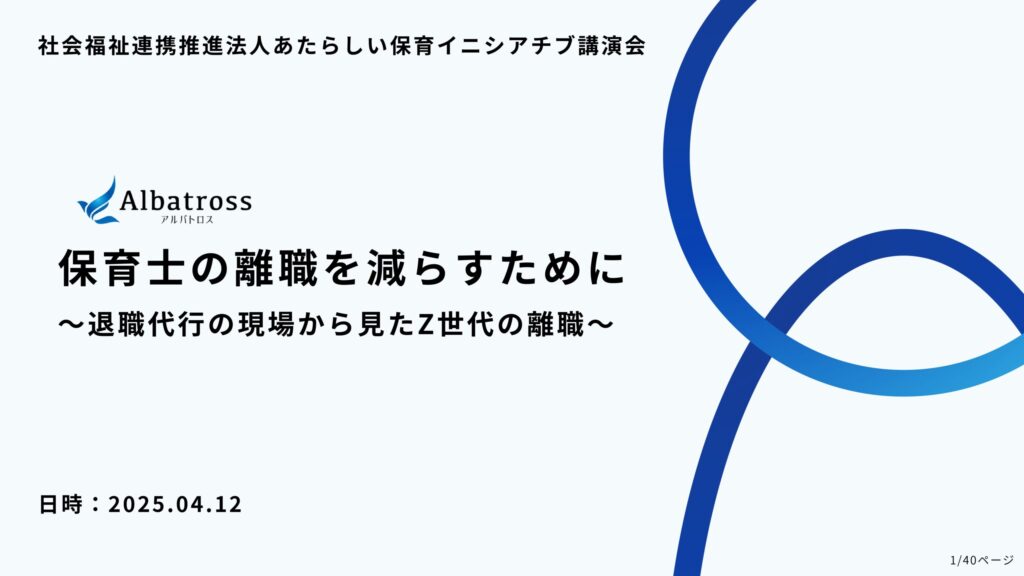
保育士の離職を減らすために
~退職代行の現場から見たZ世代の離職~
依頼趣旨
保育業界では、全国的に保育士の退職が大きな課題となっており、業界全体として対策が求められています。今回の講演では、若者世代(Z世代)の保育士の離職に焦点を当て、累計3万人以上の退職を確定してきた退職代行業者の視点から離職に至る背景やその要因を解説します。実際の退職理由に基づいたリアルな事例をもとに、Z世代の価値観や仕事観、現場でのコミュニケーションの取り方に触れながら、若手職員の定着を図るための具体的なアプローチを提案します。
講演詳細
開催日時:2025年4月12日 15:15~16:15
開催地:東京都新宿区西新宿6-3-1新宿アイランドウイング16F
参加人数:約50名
参加者:保育施設経営者(理事長)、関係企業
講師:谷本慎二(株式会社アルバトロス代表取締役/退職代行モームリ代表)
主催:社会福祉連携推進法人あたらしい保育イニシアチブ
講演内容

➀退職代行の利用者データ
サービス開始から現在に至るまでの退職代行利用者数や、実際に会社へ退職連絡をしている様子を動画で公開しました。
②保育士の利用者の退職理由
過去実際に寄せられた保育士の退職理由の一部を年齢・雇用形態・勤務年数と共に紹介しました。また、保育士の離職者の中でどのような労務問題(上司からのハラスメントやサービス残業など)が多いか実情をお伝えしました。
③Z世代の仕事に対する考え方と退職事例
Z世代という言葉の意味や、世代特有の仕事観について解説しました。また、実際に若者世代から寄せられた退職理由を紹介し、離職に至る背景や傾向について詳しくお伝えしました。
④コミュニケーションの取り方
離職を減らすにはコミュニケーションが重要であると解説し、押さえておきたいポイントや注意点についてお伝えしました。
⑤離職防止策
離職防止に向けて、弊社で実施している具体的な取り組みや、現場ですぐに実行できる施策を提案しました。
⑥まとめ
離職防止に向けた重要なポイントを、簡潔にまとめてお伝えしました。
講演会終了後の懇親会にて

講演会終了後の懇親会にて、退職代行モームリを知っているか伺ったところ、参加者の約9割が知っていると回答されていました。
保育園経営者の方々からは「ぜひ保育士に向けた講演会もしてほしい」「コンサルティングに興味がある」と多くの方にお声をいただき、大好評な講演会となりました。
また、実際に従業員がモームリを利用して退職したという声も頂き、「オペレーターの対応が丁寧で安心できた」といった感想も寄せられました。改めて、電話対応の重要性と、認識を統一して運営を徹底することの大切さを実感しました。
こうした講演や企業・学生向けのコンサルティングや相談会は、個別対応も可能です。

